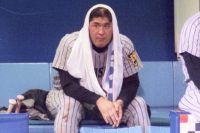驚異の0点台…2枚看板を支える“理論” 猫背型? 反り腰型? 元竜エースも推す判別法

元中日エースと東京五輪金メダリストが「鴻江理論」のメリットを語り合う
“防御率0点台”の活躍で注目の「理論」がある。西武の今井達也投手、隅田知一郎投手は、それぞれ0.51、0.98とパ・リーグの防御率1位、2位を占めているが(15日現在)、両投手の共通点といえば、オフの自主トレで師事するなどアスリートコンサルタント・鴻江寿治氏の「鴻江理論」を実践していること。それが選手・指導者にもたらすメリットとは? 同理論をサポートする骨盤ベルトとキャップのローンチイベント(デサントジャパン主催)で、同じく鴻江氏の指導を受けてきた元中日エース・吉見一起さん、女子ソフトボール金メダリストの峰幸代さん、渥美万奈さんが語ってくれた。
鴻江理論とは、骨盤の開きの左右差を基に、人の体を猫背型の「うで体」(うでからだ)と反り腰型の「あし体」(あしからだ)の2タイプに分類するというもの。改めて説明すると下記のようになる。
「うで体」…背中側から見て左肩が右肩よりも上がっている、右腰が前にかぶって左腰が開いている、重心が母指球寄り、などが特徴で、腕から動作を開始するとスムーズな動きにつながる。
「あし体」…背中側から見て右肩が左肩よりも上がっている、左腰が前にかぶって右腰が開いている、重心がかかと寄り、などが特徴で、足から動作を開始するとスムーズな動きにつながる。
吉見さんは「うで体」、峰さん、渥美さんは「あし体」タイプ。ちなみに今井投手は「あし体」で、隅田投手や、鴻江氏の指導を長く受けている女子ソフト界のレジェンド・上野由岐子投手は「うで体」だ。
吉見さん、渥美さんは腰痛、峰さんは親指の故障を機に鴻江氏と出会い、本来の自分に合うタイプの動作を学んだ。「違う体の使い方を1つ知るだけで、パフォーマンスが飛躍的に上がってくるのは初めての感覚でした」(峰さん)と感銘を受けたという。
例えばグラブやミットの使い方だけでも、両タイプでは感覚が異なる。「うで体」が苦手とする体の左側の“カベ”を投球時に意識していたという吉見さんは、「グラブを閉じるときも左手の小指と薬指を使って閉じます。親指を使うと力が入らない」と解説。確かに上から下に閉じる動きは、「うで体」のパワーポジションである猫背型に導くイメージはある。逆に華麗な内野守備が持ち味の渥美さんは「あし体タイプは親指に力を入れます。親指が下を向いた瞬間、“カベ”も意識せずに投げられます」と語る。
扇の要を務める峰さんは、「私は捕球の際、親指をグッと押し込むイメージ。逆にうで体の人は小指を使って吸収するようにミットを使います」と説明。その他、目線の上下や地面反力の使い方など、同じ超一流でも細部にわたって感覚が異なることが、実に興味深かった。

今井投手の投動作はNG? 「ダメという意識があったけれど、理に適っている」
そうなると、自分がどちらのタイプなのかが気になるが、簡単な判別法がいくつかある。
3人がお勧めするのは、椅子に座って後ろから肩甲骨付近を押してもらう方法。圧力に対して踏ん張ったときに、腹筋に力が入れば「うで体」、背筋に力が入れば「あし体」だ。他にも、椅子から立つときに膝に手をつけば「うで体」、そのまま立ち上がれば「あし体」。爪先立ちになったときに、母指球側とかかと側とで、どちらに重心を置くかも参考になる。
何より大切なのは、人それぞれに合う動きや感覚は異なると“認め合う”こと。「あし体」の今井投手は右足を跳ね上げるように投げるため、スパイクの爪先を保護するP革を使わないという。それについて吉見さんは「僕らの中では、右足の擦りが短い投手はダメという意識があったけれど、今井投手には理に適っている。同じような投げ方の子どもたちにも、『もっと地面を蹴ろうぜ』ではなく、それもありなんだと思えるようになった」と語る。
理論を知ることで、「指導の幅が格段に広がった」と口を揃えるのは峰さんと渥美さんだ。「もし、あし体の指導者が、うで体の子たちに自分の経験を押し付けたら、伸び悩んだり怪我したりするかもしれない。互いの動きを学んでおくことで、壁にぶつかった時にも救うことができます」と峰さん。
渥美さんも「ソフトボール教室で『チームでその動きをすると怒られる』という子も結構、多いんですけど、『大丈夫だからチャレンジしてみて』と。1つのやり方だけでは限界がくるかもしれない。異なる考え方を取り入れておくことは、壁を破る良いきっかけにもなると思います」と力を込める。
ちなみに渥美さんは、打撃で上野投手の速球に対応するときは「あし体」だが、他の投手には「うで体」の動作をするなど使い分けているそうだ。自分を知り、他者を認めることでプレーの幅も広がり、引き出しも増やせる。それが、「鴻江理論」の注目度が高まるゆえんなのかもしれない。
(高橋幸司 / Koji Takahashi)
球速を上げたい、打球を遠くに飛ばしたい……。「Full-Count」のきょうだいサイト「First-Pitch」では、野球少年・少女や指導者・保護者の皆さんが知りたい指導方法や、育成現場の“今”を伝えています。野球の楽しさを覚える入り口として、疑問解決への糸口として、役立つ情報を日々発信します。
■「First-Pitch」のURLはこちら
https://first-pitch.jp/