メジャーからの異例契約「その場で断りました」 日本人初は幻も…貫いたカープ愛
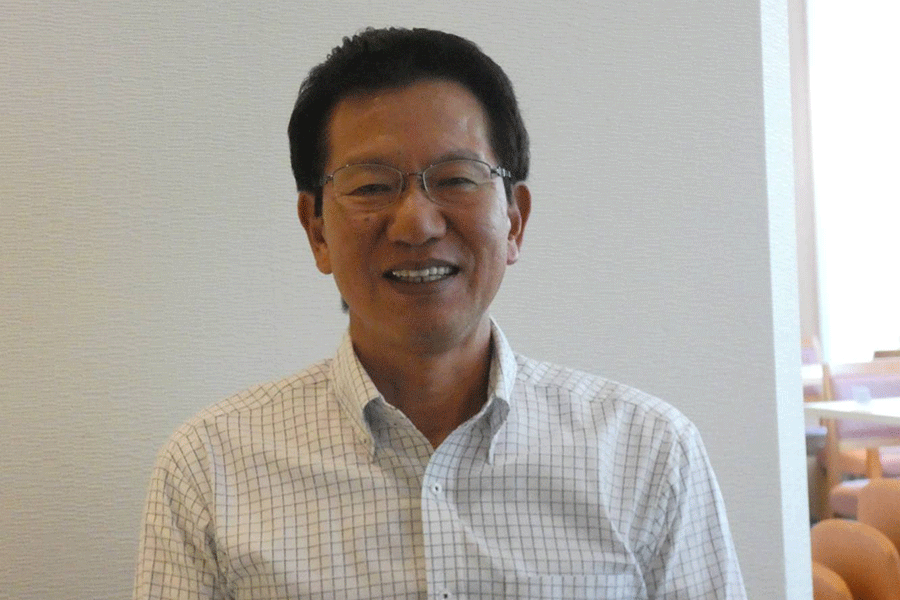
大野豊氏は1993年終盤、エンゼルスから誘いを受けた
エンゼルスには大谷翔平投手を含めて、これまで5人の日本人選手が在籍した。1997年にオリックスから移籍した長谷川滋利投手が第1号だったが、それより前の1994年に違う選手が入団する可能性があった。元広島投手の大野豊氏(広島OB会長、野球評論家)は38歳になった1993年シーズン終盤にエンゼルスから誘われていた。「自分さえお願いしますと言えば、行けたと思います」と明かした。
大野氏は1991年に再びクローザーとなり、広島のリーグ優勝に貢献した。3勝4敗で西武に屈した日本シリーズも3試合に登板して2セーブを挙げ、1点も許さなかった。プロ16年目の1992年も好調をキープ。42登板、5勝3敗でリーグ最多の26セーブをマークした。この年はかつて同僚の小林誠二氏(1988年に引退)に教えてもらい、自分なりにアレンジして使ってきたパームボールを阪神・新庄剛志外野手(現日本ハム監督)に打たれて封印したという。
1992年9月16日の阪神戦(甲子園)、0-0の8回途中から登板し、9回裏に新庄にサヨナラ2ランを浴びたのがパームボールだった。「僕の場合、独特な投げ方をしていて、パームは肘に凄く負担がかかっていた。肘の状態が悪くなってきたのもその影響かな。そろそろやめようかなと思っていたところで、新庄に打たれて封印を決めました。それ以来、二度と投げていないです。僕は駄目と思ったら思い切りがいいんですよ」。
ただし、誤算がひとつ。「甲子園に来るたびに、新庄に打たれたシーンがビジョンに流れるんですよ。それを見るのは腹が立ちましたけどね」と笑いながら話した。そんな形で9月にパームボールに“別れ”を告げたが、10月には寂しい出来事があった。10月4日の巨人戦(広島)で、長年バッテリーを組んだ同い年の達川光男捕手の引退試合が行われた。「一緒に戦ってきて彼から学ぶこともたくさんあったし、彼のリードによって勝った試合もありましたし……」。
9回表、マウンドに向かうリリーフカーに大野氏は達川氏と2人で乗って登場した。「それは球団の方で考えてくれたんじゃなかったな」と話したが、忘れられない思い出のひとコマ。やはり寂しかった。「達川がやめた後、自分が引退する夢を相当見ましたね。ああ、僕も近いのかなって思いながら、同じような夢をずっと見るんですよ。達川がやめたことが、自分の中ですごい衝撃となっていたんだなって受け止めたんですけどね」。
「お願いしますと返事すれば、行けたでしょうね」
エンゼルスからの誘いは翌1993年シーズン終盤にあったという。「あるメディア関係者の人を通じて、話がありました」。1年間のレンタルで年俸100万ドル(当時のレートで約1億1100万円)などの具体的な条件も提示されたそうだ。この年の大野氏は開幕2戦目、4月11日のヤクルト戦(神宮)から6月6日のヤクルト戦(広島)まで12試合連続セーブをマーク。シーズン7セーブ目だった4月29日のヤクルト戦(広島)では当時史上4人目の100勝100セーブを達成した。
そんな日本を代表するクローザーを、エンゼルスはこの数年前から調査し、ついに獲得に動き出した。野茂英雄氏がメジャーに移籍したのは1995年。それよりも前にメジャーリーガー・大野豊が誕生する可能性があったわけだが「話を聞いた時にもう即答。その場で断りました」と話す。「僕はカープにテスト生で入って、ここまで育ててもらった恩があるし、カープではないユニホームを着て現役を終える考えはなかったのでね」。
そもそもメジャーリーグにも興味がなかったという。「入団1、2年目にアメリカの教育リーグに行ったけど、滑る、大きい、重たい向こうのボールになじめなかった。2年目の時はバックホームでトスする時、天然芝に指を突っ込んで捻挫したりね。38歳でそういう環境でやる気持ちになれなかった。一つでも二つでもやりたいと思えるものがあれば別でしょうけど、僕の中では適用するものがなかった。だから、その話を持ち帰ることもしなかったんですよ」。
この件に関してカープ球団と話すこともなかったそうだ。「あとあと球団の方にも回りまわって、話がいったんじゃないかと思いますけど、もうすでに僕が断っていましたからね」と振り返った。「そういう目で見てもらって、評価していただいたことはありがたいことと思いましたよ。あの時、僕がお願いしますと返事すれば行けたでしょうしね」と言うが、メジャーよりもカープを第一に考えて断ったことには令和の今も後悔していない。
「向こうの感覚、環境とか野球に関して見て経験できるということはひとつの財産、引き出しを増やす要素にはなったでしょうけどね。でも行かなくてよかったと思ってます。その時の考えは今も変わりません。その選択にも悔いは全くありません」。大野氏は毅然とした表情でそう言い切った。
(山口真司 / Shinji Yamaguchi)







